| 情報家電企業の新しい差別化優位戦略 |
| -ダイナミック品質ピラミッド(DQP)戦略 |
| 舩木龍三・合田英了 |
| プリント用画面(会員専用・PDF) |
| ||||
| 1.日本の情報家電企業の競争力低下 | ||||
|
かつて、半導体やAV機器で世界を席巻した日本の情報家電企業が危機にたたされている。 ひとつは、半導体で強さを誇ったNEC、富士通が、連続赤字から債務超過の危機に直面していることだ。2003年3月期決算は、富士通が1,220億円、NECが245億円の最終赤字を計上し、いずれも二期連続の赤字となった。両社はここ数年、半導体の主力であるDRAMにおいて、サムスンを始めとするアジア企業のキャッチアップにあい、急速にシェアを低下させた(図表1)。人員削減や工場閉鎖により巨額の特別損失を計上したことで、連続赤字となった。ところが、この背後には赤字以上の問題が横たわっている。繰延資産問題である。両社はこれまで、貸倒引当金やリストラ費用等、会計上先を見越して将来の損失を費用としたものが、税金の計算上は、実際に損失が生じるまで認められないために、余分に支払っている税金を「前払い(国に対する資産)」としてバランスシートの資産の部に計上してきた。この制度のおかげで、巨額の特別損失を計上しても自己資本が潤沢にみえるという仕掛けになっている。富士通は2003年3月期に純額ベースで3,400億円、NECは約3,000億円を積み上げた。ところが、赤字で税金が払えない企業が繰延税金資産を計上することは許されない。繰延税金資産を将来取り戻すためには、将来の黒字が前提になる。将来黒字になり支払うべき税金があってはじめて繰延べた税金が相殺されるからだ。このため翌会計以降も赤字が続く場合には、監査法人の要求によって取り崩しを余儀なくされ、一気に債務超過に陥ることになる。繰延税金資産問題で公的資金注入を受けた「りそな」と同じ危機にさらされるのだ。
ふたつは、ブロードバンドネットワークカンパニー構想のもと、不況下の90年代、成長を続けてきたソニーが本業のエレクトロニクス事業の低迷等から、業績悪化、株価低迷に陥っていることである。2003年3月期のエレクトロニクス事業の売上高は4兆9,405億円(前年比93.5%)、営業利益は414億円と前年の赤字から黒字に転じたが、営業利益率は1%に満たない状況だ。ソニー製デバイスを内製するビデオカメラやデジタルカメラ、カメラ付携帯電話では10数%の高い営業利益率だが、液晶パネルを外製(LG電子)に頼るテレビや、CPU、HDDなど大半のデバイスを外部に依存するバイオの収益率は低い。先頃液晶パネルの自社生産を視野に入れた投資プランを発表したが、シャープ、サムスン等が数千億円の巨額投資をし、第六世代、第七世代の大型ラインの建設に踏み切る今、あまりにも遅すぎるテレビ戦略の転換である。しかも低コスト化のために中国に生産をシフトしたことも裏目にでた。ソニーの本来の強さである小型実装技術をいかした「軽薄短小」のモノづくり力が低下している。例えばバイオ505の厚さは、一時は19.8mmまで薄くなっていたが、生産を中国に移管したあと33.5mmに増した。最新の「Z」でさえ厚さ23.8mm・2.1kgである。競争相手のシャープムラマサが13.7mm・0.95kg、レッツノートが23.5mm・0.99kgという状況下でソニーのノートPC群はモバイルとしての競争力を失った。ビデオカメラの製造も生産リードタイムの遅さから機会ロスを招き、日本に生産機能を戻すなど迷走している。好調なのはデジカメやカメラ付携帯だけだ。ソニーはここ数年、ブロードバンド時代を見据え、四つのゲートウェイ(ベガ、バイオ、PS2、携帯電話)を通じて、音楽や映画などのコンテンツを提供するビジネスに向けた布石を着実にうってきた。新しいAV/ITライフを創造する構想は評価でき、間違いはなかったと考えられるが、部品や組立の外部化を図り生産を効率化させ、ブランドと付加価値によって高付加価値・高マージンを取り込み、売った後もコンテンツやサービスで儲ける算段が、根幹のハード領域での失策により、ゆらいでいる。 現在、世界の多くのAV・情報機器市場で日本の企業のシェアが低下している(図表2)。カラーテレビやステレオセット等の旧技術市場だけでなく、プラズマテレビやDVDプレーヤー/レコーダー等、新技術市場でもシェアを落としている。業績悪化、復活の糸口がみえず苦しむ日本企業はここに取り上げた3社だけではない。世界的なシェアの低下は日本の情報家電産業に共通する問題である。日本の情報家電産業はなぜ危機に直面しているのか、その要因を明らかにし、復活に向けた戦略を提案したい。
| ||||
|
本稿は当社代表・松田久一からの貴重な助言のもとに執筆されました。ここに謝意を表します。あり得べき誤りは筆者の責に帰します。 |
| 本コンテンツの全文は、メンバーシップサービスでのご提供となっております。 以降の閲覧には会員サービスご登録が必要です。
|

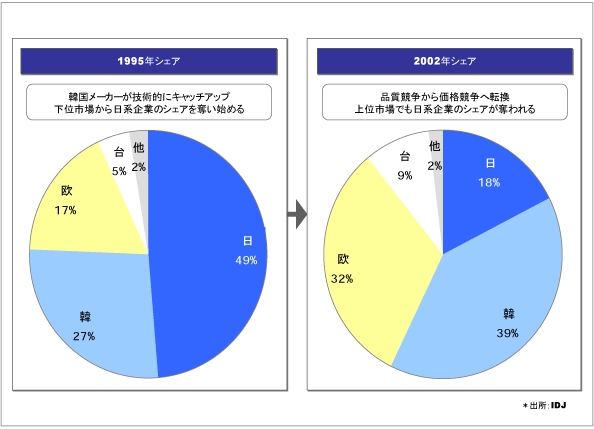
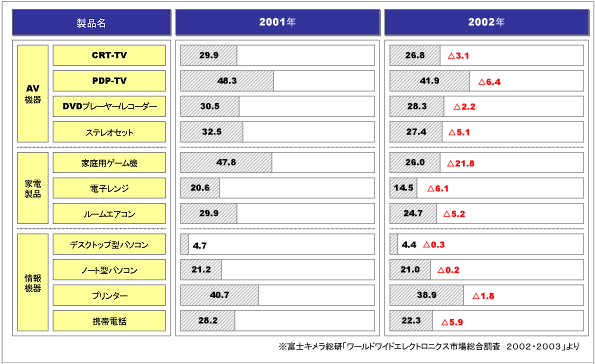

![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)



