同日使用したプレゼンテーションをもとに構成したものです。
図表1.グローバルな市場拡大のマーケティング |
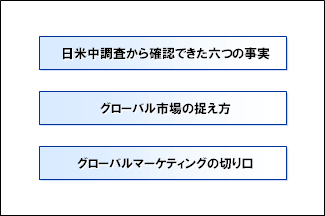 |
まず、日米中3カ国調査から明らかになったポイントをご案内させていただきます。
日米中の3カ国の違いを、AV機器を中心にご案内いたします。
(1)持っているものが違う
図表2.AV機器の所有率は各国で異なる |
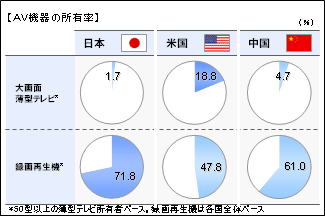 |
これは、「大画面薄型テレビ(50インチ以上)」、「録画再生機」の日米中の各国別の所有率を表したものです。「大画面薄型テレビ」の所有率をみますと、米国では薄型テレビ所有者のうち、約2割が大画面のものを所有しており、日本、中国と比較して高いことがわかります。日本では2%にとどまっていますが、今回の調査対象者である日本人の所得水準が、米国と比較して著しく低いわけではありません。また「録画再生機」は、米国が5割、中国が6割なのに対し、日本では7割を超え、所有率が高くなっています。
「携帯電話」や「携帯音楽プレーヤー」の所有率、ふだん持ち歩いている人の比率にも3カ国で違いがあり、所有率、持ち歩く人の比率、いずれも日本で高くなっています。
(2)使い方が違う
図表3.AV視聴スタイルは国により異なる |
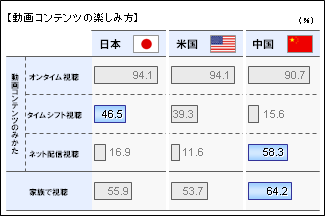 |
「動画コンテンツの見方」は、放送時間に視聴する「オンタイム視聴」が、3カ国とも基本の視聴スタイルとなっていますが、放送時間外に録画した番組を視聴する「タイムシフト視聴」は、日本で約5割と高くなっています。
日本ではテレビ番組などの動画コンテンツは、地上波での1回きりの放送が主流であるのに対し、米国ではケーブル・衛星放送の普及が進んでおり、多チャンネル、複数回放送が主流になっています。このような放送形態の違いから、日本で「タイムシフト視聴」が高くなっていると考えられます。また中国では、「ネット配信視聴」が58%と高くなっています。日本のテレビドラマが、ほとんどタイムラグなく中国語の字幕付きでネット配信されるところからも、中国でのネット視聴の浸透が理解できるかと思います。
コンテンツを一緒に視聴する人、という観点でも、3カ国で違いが確認でき、「家族での視聴」は、中国で高くなっています。3カ国の1世帯あたり平均人数は、日・米が3人弱なのに対し、中国では4人と多く、世帯人数が、家族意識とともに視聴スタイルに影響を与えていると考えられます。
(3)使う場所が違う
図表4.利用シーンと使う機能が異なる |
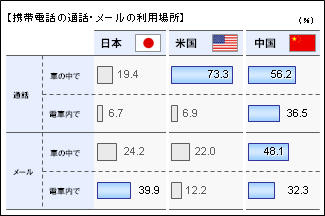 |
携帯電話の使い方をみると、日本では、「電車内でメール」に特徴があります。電車に乗ったらまずケータイを取り出して、メールを確認・送受信する、という光景は、日常的によく目にするものかと思います。このような使い方には、日本では電車での通勤・通学スタイルが浸透していることが影響していると考えられます。また、満員電車の中でケータイの画面に没頭していても安心な社会、ということもあるかもしれません。
米国では、「車の中で通話」が7割を超えています。米国は車社会であることに加えて、メールではなく電話、というコミュニケーションのとり方の違いも背景として考えられます。また、日本がテンキー文化なのに対して、タイプライターやパソコンのフルキーの使用が浸透していることもあるかと思います。
中国では、携帯電話は「いつでも」「どこでも」という使い方のようです。「電車内で通話」も約4割となっており、通話とメールのほかにも、音楽視聴やゲームなどの利用も高く、暇さえあれば何かしらケータイをいじっている、というイメージです。
| 本コンテンツの全文は、会員サービスでのご提供となっております。 以降の閲覧には会員サービスご登録が必要です。
|
NEXT VISION 2009 基調講演


![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)



