
カニバリゼーション(cannibalization)とは、自社の商品が自社の他の商品を侵食してしまう「共食い」現象のことをいいます。カニバリゼーションには本来「人食い・共食い」という意味があります。
新商品の導入による既存商品の売上減少、売場でのフェース展開の行き過ぎによる自社商品の売上減少、新規チャネルによる既存チャネルの侵食などがあげられます。
既にカニバリゼーションが発生している場合には、商品ラインを見直し拡大を抑制する、商品の違いを顧客に認識させるといったことが必要になります。
新たに商品を導入する場合には、既存の商品とは異なるチャネルで展開する、異なるターゲットを狙うといったことが必要になります。
競合企業のカニバリゼーションを創出することで、自社の市場シェアを拡大させることも考えられます。
市場シェアの高いリーダー企業に対して、その企業の主力商品・事業と共食い現象を起こさせるような商品の発売・事業への参入を仕掛け、その商品カテゴリー拡大の可能性があるにも関わらずカニバリゼーションを危惧するリーダー企業に参入への早期判断を鈍らせることで、シェアを奪取していくという戦略です。
「消費社会白書2025」のご案内
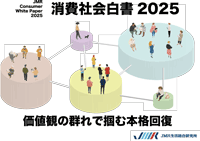
30年の長いトンネルを抜けて、そこは「灼熱の真冬」だった。2024年の消費は、経済史において消費転換の年だったと明記されるかもしれない。
無料の会員登録をするだけで、
最新の戦略ケースや豊富で鮮度あるコンテンツを見ることができます。
参照コンテンツ
- 戦略ケース スイーツ市場を取り込んで快進撃を続けるハーゲンダッツドルチェ(2007年)
- 戦略ケース ホームデポ 米国最強小売業のeリテイル戦略(2000年)
- 戦略ケース 日本マクドナルド株式会社 「外食マーケット5%奪取に向けたエリア戦略」(1999年)
関連用語
おすすめ新着記事

MNEXT 価値の根拠は何か―欲望を充当するもの(要約版)
経営やマーケティング、そして、消費者心理学でも、曖昧に扱われている「ニーズ、ウォンツ、欲求、欲望」などの概念を整理しています。

MNEXT 日本人消滅論の錯覚―世相批判の論理(2024年)
経営には、新紙幣になった渋沢栄一のような儒教倫理も必要なく、哲学史も必要ではなく、本当に到達する道筋、つまり、論理性が必要である。さらに、それを独自に突き詰めていく力が必要である。この意味で哲学は必要だ。経営者は、学者と異なり、学問的には何にも縛られない。そこが経営者の思想の自由の強みである。ミクロな視点でマクロを語れない。しかし、マクロな視点の再構築は、ミクロな現実にしかない。ミクロを熟知し、錯覚せずに、現実からくみ上げられた知識が、マクロな日本経済を再生する力になる。日本人消滅論は錯覚だ。

MNEXT 円安は歓迎すべきかー過熱する円安論争
円安歓迎論と是正論の論戦が燃え上がっている。消費動向に一家言ある者として、再び、消費には過剰な円安は害あって一利なし、景気にもよくないという立場だ。少々、交通整理をして、論理を検証してみよう。
おすすめ新着記事

「食と生活」のマンスリー・ニュースレター チョコレートの今後購入意向は80%以上! 意外にも男性20~30代と管理職が市場を牽引
チョコレート商品の値上げが続くなか、成分や機能を訴求したチョコレートが伸びている。今回はどのような人がどんな理由でチョコレートを食べているのか調査した。

成長市場を探せ キャッシュレス決済のなかでも圧倒的なボリュームを誇るクレジットカード決済は、2024年、3年連続の2桁成長で過去最高を連続更新するとともに、初の100兆円台にのせた。ネットショッピングの浸透も拡大に拍車をかけている。 キャッシュレス市場の雄、クレジットカードは3年連続過去最高更新(2025年)
キャッシュレス決済のなかでも圧倒的なボリュームを誇るクレジットカード決済は、2024年、3年連続の2桁成長で過去最高を連続更新するとともに、初の100兆円台にのせた。ネットショッピングの浸透も拡大に拍車をかけている。

消費者調査データ トップは「ドライゼロ」、2位を争う「オールフリー」「のんある気分」
アップトレンドが続くノンアルコール飲料。調査結果は「アサヒ ドライゼロ」が首位を獲得、上位にはビールテイストが目立つなかで、「のんある気分」が健闘している。再購入意向では10位内にワインテイストやカクテルテイストの商品も食い込み、ジャンルとしての広がりを感じさせる。





![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)



