日本の人口は2006年をピークに減少すると言われている。その一方で、人口増加が見込まれている都道府県がある。具体的には、東京、埼玉、神奈川、千葉といった首都圏や、福岡、愛知、兵庫等の地方の都市圏である(図表1)。都道府県を個別にみれば、人口成長には格差がある。成長する都道府県でいかに自社商品の売上を伸ばすか。それは都道府県レベルからもう一歩ブレークダウンして、商圏レベルに細分化し、成長性が高く自社シェアが低い商圏・店舗を特定し、マーケットチャンスを掴むことから始まる。
図表1.日本の人口予測
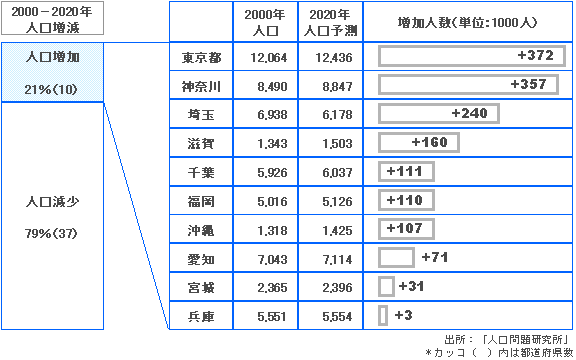
図表2.商圏プロット図
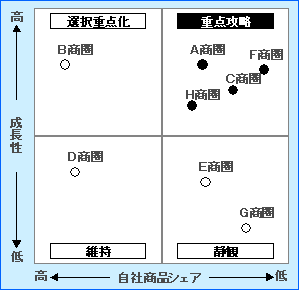
まず、自社商品の商品別に図表2のような商圏のプロット図をつくってみる。この中で最も優先度が高いのは重点攻略商圏であり、このゾーンにある商圏から売れない原因を調べてみる。一般的には、商品不振の原因のほとんどは流通にある。その商圏に供給している卸流通が弱いとか、キーとなる拠点店が競合品に力を入れている等というのが主な原因だ。重点攻略商圏が特定できたら、商圏内の拠点店から当該商品カテゴリーの売上・成長性をヒアリングして、自社のインストアシェアを計算し、図表2を使って今度は重点攻略商圏内の店舗をプロットしてみる。すると、ゾーンごとの店頭戦略は次のように考えればよいことになる。
【重点攻略拠点】
店の成長性が高いが、自社のシェアが低い店舗。ヒットプロモーションで信頼をつくり、提案棚替え期にあわせた機動的な提案で店内での露出をあげていく活動が大切である。価格も競合品と比べて劣るようであれば特定シーズンでの低価格対応も考える。
【選択重点拠点】
店の成長性が高く、自社シェアが高い店舗。競合の浸食をくい止めるために、売場レイアウト、棚割、年間の販促・売場展開プラン等広く深いソリューションを提供し、店の信頼をしっかりと獲得しておく。
【維持拠点】
自社商品のシェアは高いが、店の成長性が低い店舗。店の当該商品カテゴリーの成長性が低いということは、ターゲット層が少ないか、注力度が低いか、どちらかである。前者なら品揃えの転換策を、後者ならカテゴリーの魅力や売り方を啓蒙し注力度をあげる。
【静観拠点】
自社商品のシェアが低く、店の成長性も低い店舗。当面現状維持。成長が見込めない場合は、訪問頻度を減らし、手間もお金もかけないようにするのが得策だ。
全体平均ばかりみていては、動けない。担当するテリトリーのマーケットチャンスを発見し、チャンスをモノにする最短の道筋をみつけ行動することが大切である。
参照コンテンツ
おすすめ新着記事

「食と生活」のマンスリー・ニュースレター チョコレートの今後購入意向は80%以上! 意外にも男性20~30代と管理職が市場を牽引
チョコレート商品の値上げが続くなか、成分や機能を訴求したチョコレートが伸びている。今回はどのような人がどんな理由でチョコレートを食べているのか調査した。

成長市場を探せ キャッシュレス決済のなかでも圧倒的なボリュームを誇るクレジットカード決済は、2024年、3年連続の2桁成長で過去最高を連続更新するとともに、初の100兆円台にのせた。ネットショッピングの浸透も拡大に拍車をかけている。 キャッシュレス市場の雄、クレジットカードは3年連続過去最高更新(2025年)
キャッシュレス決済のなかでも圧倒的なボリュームを誇るクレジットカード決済は、2024年、3年連続の2桁成長で過去最高を連続更新するとともに、初の100兆円台にのせた。ネットショッピングの浸透も拡大に拍車をかけている。

消費者調査データ トップは「ドライゼロ」、2位を争う「オールフリー」「のんある気分」
アップトレンドが続くノンアルコール飲料。調査結果は「アサヒ ドライゼロ」が首位を獲得、上位にはビールテイストが目立つなかで、「のんある気分」が健闘している。再購入意向では10位内にワインテイストやカクテルテイストの商品も食い込み、ジャンルとしての広がりを感じさせる。





![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)



