| 中国におけるコンビニ業態の現状 | |
| ‐石油関連会社の進出が加速 | |
| 楊 亮 | |
|
コンビニエンスストア(以下コンビニ)は中国で「便利店」と呼ばれている。中国最初の便利店は新しい業態として、1987年広州市で地元資本により誕生した。以降四半世紀を経て、現在では中国全土で約6万6,000店舗(トップ44社の合計)の小売業態にまで成長した。 2013年9月に中国チェーン企業協会は、2012年中国コンビニ企業トップ44社を発表した。外資系としてもっとも早く中国市場に進出したセブン-イレブンは、1,732店舗で7位にランクインしている。他にランクインした日系企業は、ファミリーマート(14位、1,008店舗)、ローソン(28位、362店舗)である。 日系企業の動き
ファミリーマートは、2004年に上海に進出、その後広州、蘇州と杭州に店舗を展開している。2011年、「康師傅」などを傘下に持つ台湾頂新グループが、「ファミリーマート中国」の株式の59.65%を取得し、日本ファミリーマートと台湾ファミリーマートに代わって、実質的に「ファミリーマート中国」の運営権を獲得した。2012年2月末まで、ファミリーマートの800店舗のうち、約640店舗は上海に集中し、上海でもっとも多い店舗数を展開している外資系企業である。同社は2012年6月に成都に進出。今後、北京、武漢、深センなどへの展開を計画している。 ローソンは1996年、上海百聯グループと合資会社「上海ローソン有限公司」を設立、97年に1号店を出店した。2004年に経営現地化のため、「上海ローソン」のローソン持分比率を49%まで下げたが、2011年には85%に引き上げ、再び経営権を取得した。ローソンは中国進出は早かったものの、上海292店舗、重慶70店舗、大連13店舗、北京3店舗(2013年9月末現在)と出店スピードは比較的ゆっくりだったが、2012年に「ローソン中国投資有限公司」を設立、上海ローソンを傘下におさめ、重慶、北京などでも地域の投資子会社を通じて積極出店を図る考えだ。 中国石油会社の参入
トップの中石化販売は、非石油製品の事業開発戦略として2008年にコンビニエンスストアに参入した。消費者の多元化したニーズを満たすには、非石油製品事業の開発が必要だと判断したからである。海外同業者のノウハウを吸収し、「易捷便利」というブランドを打ち出した。中国全土で自社経営のガソリンスタンドに併設、運営・管理モデルを統一して展開している。同社の2012年決算報告書によると、非石油製品事業の売上が110億元、5年間で売上10倍という飛躍的な成長を遂げた。しかも中石化販売は中国国内21省で、3万800店のガソリンスタンドを経営、コンビニ出店の余地はまだ大きいと推測できる。 しかし、1店舗あたりの販売力を見ると、1万9,200店舗に対して、非石油製品事業の売上は82憶6,000元で、単店の1日当たりの売上は、1,195元(2万円未満)という計算になる(2011年決算報告書)。他社のコンビニの売上、6,000元(約9.6万円)と比較して1/5程度にとどまっている。 2位の中石油販売は、2011年に自社経営のガソリンスタンド1万9,000店のうち1万軒あまりに「崑崙好客」を出店し、2011年の非石油製品事業収入は64億1,000元である。 中国の国内高速道路網の総延長は9万5,600キロに達している(2012年)。今後も自動車人口はさらに増加するとみられ、ガソリンスタンドコンビニの利用人口も増えると予測できる。ガソリンスタンドへのコンビニ併設は、既存店舗の資源を活用することで、新たな店舗賃貸料や人件費が不要のため、低コストでの出店が可能である。さらに、伝統的なコンビニの経営と比較すると、一部の地域で慣行となっていた「進場費」(サプライヤーが小売チェーンに商品を供給する際に、小売チェーンに払うリベート)、「上架費」(棚代)などのリベートが不要のため、メーカーにとって取引条件が良いというメリットがある。今後、中石化販売と中石油販売は、このメリットを活かして、メーカーとともに顧客が魅力を感じる商品の開発を通じて売上をどう伸ばすかが事業拡大のカギである。 (2013.11)
|
| Tweet |
|
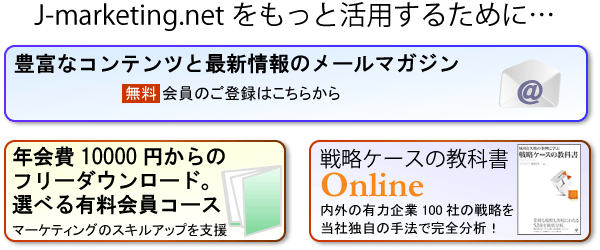




![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)



