日本の小売業が外資系参入の脅威にさらされている。外資系参入で、この1年、最も変わったのは、日本の小売業である。それまでの価格訴求からの脱却である。こうした変化を機敏に感じ取り、他社に先駆けて提案することが営業に求められている。どういう点が変わったか?四つのキーワードを取り上げ、提案チャンスを提示したい。
第一は「加工度アップ」。これは食品の世界ではミールソリューションなど以前から言われていることであるが、改めて力を入れようとしている。食品で言えば総菜部門であるが、ここの提案が鍵を握りつつある。他業界では応用しにくいと考えられるが、拡大解釈すれば売りのカスタマイズ化を提案することが必要となる。あるドラッグストアではNBのPB化と称して、単品販売から顧客ニーズにあわせたシステム使用提案を始めている。靴の世界ではシューフィッターを置く店が人気だ。パソコンであれば、ネット上でのカスタマイズ化は常識である。
第二は「時間節約」。買物が苦痛になったと言われて久しい。某スーパーでは滞店時間が12分と10年前の約半分に短縮化している(図表1)。この間、売場面積は約1.5倍になっているにもかかわらずだ。CVSだと平均3~4分と言われている。この短い買物時間のなかでのポイントは、客導線を見極めて目につきやすい売場を確保することである。島陳列やワゴン陳列は当たり前であるが、新しい売場を開発・提案することだ。あるメーカーは客導線の太い中通路でのエンドサイド什器を提案しているし、CVSでの島陳列なども一部企業で採用され始めている。レジ前・周辺も有効活用する余地が残されている。
第三は「情報性」。これはただ単にモノを置いているだけではダメで、手をかけないと売れないという認識からきている。具体的には情報提供ということになるが、情報の中身である。生鮮における生産者の顔写真付きというのは当たり前であるが、あるCVSではアルバイトにPOPを書いてもらうことで成果を出している。ポイントは商品の使い方提案がどれだけできるかである。サイレントチャネルと言われたCVSでさえ情報付加型販売を模索している。ひとつはレジ前での一言メッセージでもう1品購入してもらうようにしていること、もうひとつは積極的なPOP展開である。先入観を捨てて情報付加の重要性を訴求することが必要だ。
第四は「クロスMD」。これは以前(第1回、第4回)にも述べてきたが、顧客への生活提案を強化すると同時に、小売業にとっては買上げ点数を上げることで客単価増を狙うものである。方法は、カテゴリー内で自社商品以外も含めた複数アイテム陳列での売場展開、カテゴリー間を横断させた生活シーン提案型の売場展開、自社製品を総合的に品揃えしたメーカーフェアの三つがある。
アメリカでは「価格訴求は禁じ手」というのが暗黙の了解になっているという。ウォルマートには勝てないからである。日本の小売業も、価格競争ができるごく一部の企業以外は、こうした方向に向かいつつある。変化を感じ取るには店頭現場へ行かないとわからない。新しくできた店舗を見に行き、変化を感じ取り、商談に活かしていくことが必要である。そうすればバイヤーや店長に情報力で優位に立ち、「役に立つヤツ」という信頼を勝ち取ることができ、商談もスムースに進むはずである。
図表.スーパーの滞店時間と1店当り売場面積
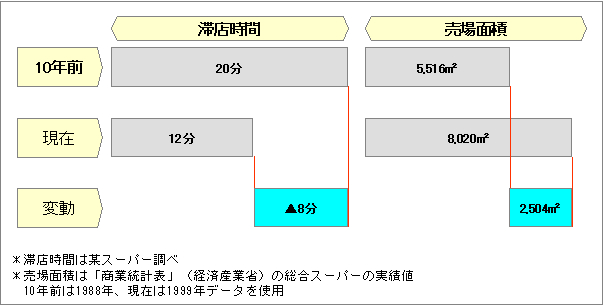
おすすめ新着記事

消費者調査データ カップめん(2025年4月版)別次元の強さ「カップヌードル」、2位争いは和風麺
調査結果をみると、「カップヌードル」が、ほぼ全員に認知があり、4分の3に購入経験があり、半数弱が3ヶ月以内に購入、と圧倒的な強さをみせるなど、ロングセラーブランドへの上位集中が鮮明な結果となった。背景には、昨今の値上げ続きで強まる消費者の節約志向があると考えられる。「失敗したくない」という意識が安心感のあるブランドに向かっているのだ。

「食と生活」のマンスリー・ニュースレター チョコレートの今後購入意向は80%以上! 意外にも男性20~30代と管理職が市場を牽引
チョコレート商品の値上げが続くなか、成分や機能を訴求したチョコレートが伸びている。今回はどのような人がどんな理由でチョコレートを食べているのか調査した。

成長市場を探せ キャッシュレス決済のなかでも圧倒的なボリュームを誇るクレジットカード決済は、2024年、3年連続の2桁成長で過去最高を連続更新するとともに、初の100兆円台にのせた。ネットショッピングの浸透も拡大に拍車をかけている。 キャッシュレス市場の雄、クレジットカードは3年連続過去最高更新(2025年)
キャッシュレス決済のなかでも圧倒的なボリュームを誇るクレジットカード決済は、2024年、3年連続の2桁成長で過去最高を連続更新するとともに、初の100兆円台にのせた。ネットショッピングの浸透も拡大に拍車をかけている。





![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)



